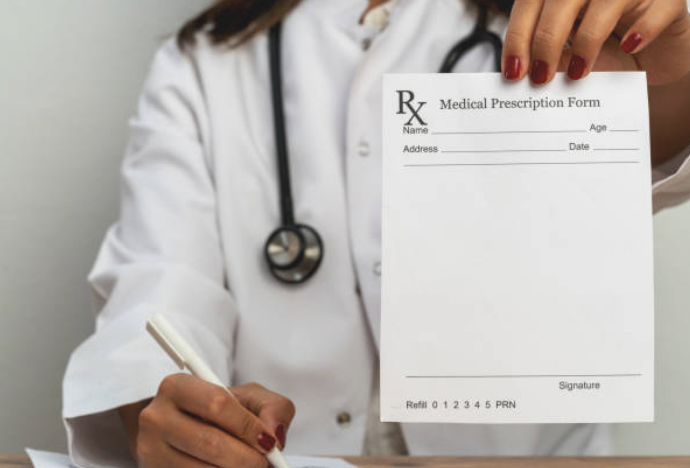(企業向け)従業員が休職・復職する際の産業医面談は意味がありますか?
記事(企業向け)
2023年8月22日

複数の企業で、
・突然従業員が会社に来なくなって休職すると言っている!
・問題のある休職中の従業員が復職したいと言ってきた!
といったお困りごとが生じることがありますが、
休職・復職のフローにはスタンダードな方法があるのでしょうか?
ある程度休職・復職の過程を見てきた人事の方からも、
・産業医が面談しても結局かかりつけの主治医の診断書と同じにするんでしょ?意味ある?
・産業医は従業員の味方?企業の味方?
・産業医の意見書と主治医の診断書の内容が違うけど、結局どうすればいい?
など多くの質問や心配事をお聞きしております。
本来は、従業員が休職となる前に対策や予防が可能であればよいのですが、
休職・復職となってしまった場合は、一定の方法で対処する必要があります。
企業を法的に守り、生産性を落とさないためにも、従業員がメリットを享受できるようにするためにも、
まずは復職プログラムに沿った休職、復職の手続きを進める必要があります。
リンク先は厚生労働省が公表している資料で、
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf
さらに簡単にお知りになりたい場合は、
こちらのリンク先のこころの耳のページも大変参考になります。
https://kokoro.mhlw.go.jp/return-to-work/data/e-learning.pdf
基本的には
1 病気休業開始及び休業中のケア
2 主治医による職場復帰可能の判断
3 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
4 最終的な職場復帰の決定
5 職場復帰後のフォロー
という5段階のステップにより、休職・復職過程を経ます。
従業員の休業中は、ケアを欠かさず実施して復職に向け、
かかりつけの医師が記載した診断書を提出してもらい、
産業医が従業員と面談して意見書を記載、
労働時間・内容などを考慮して職場復帰支援プランを作成し、
復職後も継続してフォロー、
という手順が一般的です。
厚生労働省が掲載している職場復帰支援プランの作成例はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000198527.docx
産業医が記載する「意見書」は、かかりつけの主治医が記載する
診断書と同様、企業が対象の従業員に対して安全配慮義務を
果たしているという点で重要な役割を持つものです。
産業医が意見書を記載する際には、もちろん診断書の内容は参考にしますが、
産業医は、かかりつけ医が判断困難となりがちな企業において就労するという事情を考慮し、
可能な限り企業側、従業員側双方にメリットがあるよう配慮しています。
かかりつけ医からの情報が不足していると判断した際には、
産業医は、かかりつけ医に対して、診療情報提供依頼書を送付し、
個人情報に配慮した上で、かかりつけ医と連携して意見書を記載します。
産業医選任が必須でない企業においても、従業員の休職・復職過程で、
産業医は大きく企業の生産性に貢献し得るので、ご参考になりましたら幸いです。
この記事の関連記事