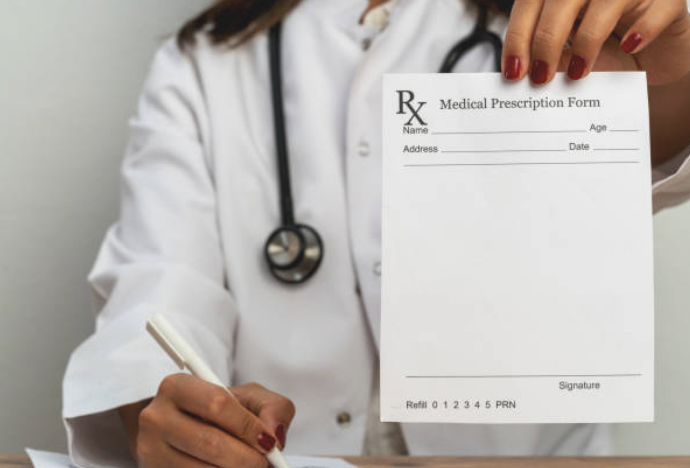(企業向け)健康診断を受けさせないと罰則があるって本当ですか?
記事(企業向け)
2023年8月29日

複数の企業から
「従業員の健康診断の取りまとめ方がよくわからない!」
「どこまですれば罰則受けずに済むのか知りたい!」
「健康診断てそもそも個人の問題じゃない?」
などのご意見をよく耳にします。
健康診断は、従業員の重大な疾患等を未然に防ぎ、企業で継続してパフォーマンスを発揮してもらうのに重要です。
健康診断を正しく取り扱えていないと、労働安全衛生法などに違反して罰則をもらうのに加え、
安全配慮義務違反として各種賠償請求を受ける場合もあり、さらに業務上の過失により刑事事件となる可能性があり要注意です。
しかし、基本的な事項を遵守していれば、こうした事態を可能な限り避けられる上、
法的にも企業を守り、従業員も健康で勤務を継続できます。
まずは、
「一般的な定期健康診断を受ける必要がある従業員は全員ですか?」という質問に対して、
答えは、常時使用される労働者(*)は必須、となります(労働安全衛生規則第43条、第44条)。
(*)常時使用される労働者とは?
→「1年以上雇用することが見込まれる労働者、1年以上雇用されている労働者で、常勤労働時間の4分の3以上労働している者」です。なお、定期健康診断では、派遣されている者は派遣元で実施します。
つまり、アルバイトとして雇用されている従業員であっても、この条件に当てはまれば、事業者は健康診断を受けさせる義務があります。
これに違反した場合、労働安全衛生法により、事業者を、50万円以下の罰金に処するとあります。
しかし、事業者が受けさせたくても、従業員が断固として受けないという事態もあるかと思います。
労働安全衛生法では、従業員は健康診断を受ける義務がある(第66条第5項)と定められていますが、
事業者側とは異なり、罰則がありません。
健康診断を受けてくれない従業員がいる場合、話し合いで解決しない時は、
その従業員に健康診断の重要性を説明した旨、受けない理由を教えてもらい、記録を残します。
また、このままだと会社が罰せられることがあるので、就業規則により従業員の処遇を決定することで対処することも考えられます。
さらに、常時使用する従業員が50名以上の事業者は、定期健康診断の結果が揃ったら、
遅滞なく所轄の労働基準監督署へ書面で報告することが義務付けられています(労働安全衛生規則第52条)。
報告にはこちらのテンプレートを使用します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/dl/18_12.pdf
ここで、有所見者数を記載する際に、有所見者の定義に迷われるかと思いますが、実際規定はありません。
労働基準監督署によれば、有所見者に総合判定が経過観察の者を含むか、要精密検査のみとするかなどは、企業や産業医の判断に任せると回答されています。
また、総合判定が治療中となっていることもあり、わからない場合は産業医と相談しながら有所見者を数える方が安心です。
産業医の氏名及び所属機関の欄に関しては、最近は産業医が記載する必要はなく、どなたでも記載可能で捺印は不要です。
さらに事業者に義務付けられていることがあります。
健康診断個人票を作成して5年間保存しておくことです(労働安全衛生規則第51条)。
これに違反すると罰則があり、50万円以下の罰金が科されることがありますので要注意です。
健康診断個人票は基本的にはこちらのテンプレートを使用します。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/var/rev0/0110/4068/2011518134157.pdf
ただし、個人票作成の方法は任意でよいとされており、必ずしもこのテンプレートを使用する必要はありません。
また、個人票作成に関しては、労働安全衛生規則等に規定があるものの、様式の項目が揃っていれば、
事実上健康診断の結果をそのまま5年間保存することで代替していてもやむを得ない可能性がある旨を労働基準監督署から回答されています。
さらに事業者に義務付けられていることを紹介します。
健康診断実施日から3ヵ月以内に実施する医師への意見聴取です(就労判定、労働安全衛生規則第51条の2)。
就労可能か、就労を制限して条件を決定する必要があるか、就労を不可とするか等を産業医等が意見します。
また、この意見をもとに事業者が従業員の就労条件を判断します。
これらの実施に関しては明確な罰則はありませんが、就労判定を実施していない状態で、
従業員の健康に問題あった場合や労災時に、安全配慮義務違反、業務上過失傷害等となる可能性があります。
また、産業医の意見と異なる条件での勤務とした場合も、注意が必要です。
よくある誤りとしては、常時使用する従業員が50名以上いないから就労判定は必要ないとするというもので、
50名未満の従業員数の事業所であっても、健康診断を実施した際就労判定する必要があります。
とは言っても産業医を選任していませんよという場合は、地域産業保健センターなどで無料で実施してもらえます。
もちろん、お近くの医師、産業医に相談することでも可能です。
健康診断の実施から事後措置までをまとめますと、
→事業者が健康診断を事業者費用負担で実施
→健康診断の結果を遅滞なく労働者に通知、または労働者から既に実施した結果を提出してもらう(*)
→結果、個人票を5年間保存(*)、要配慮個人情報(守秘義務あり)
→常時50名以上の従業員を使用する事業所は、定期健康診断の結果集計を、書面により労働基準監督署へ提出
→医師への意見聴取(就労判定)を健康診断実施日から3ヶ月以内に実施
→健康診断後の就業に関する措置(通常勤務、就業制限、就業不可等)を決定する
→有所見者に対して受診勧奨(努力義務)して2次健康診断実施
→2次健康診断後の報告を従業員に書面などでしてもらう
(*)健康診断の結果を労働者に通知しない、健康診断個人票を5年間保管しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。
健康診断の種類は、定期健康診断のみではなく、雇入れ時の健康診断、特定業務従事者健康診断、有害業務に関する各種特殊健康診断などがあります。
こうした健康診断に関しましては、また他の機会に記事として記載する予定です。
ご不明点等ございましたら、ご遠慮なくお聞き頂ければ幸いです。
この記事の関連記事