有害かも知れない化学物質を扱ってますがどうしたらいいでしょうか?
記事(全体向け)
2024年7月2日

「ぱっと見て法的な規制に該当しなさそうだったので何もしていませんが、対象物質と指摘されてしまいました。」
「有害な化学物質への対処や規制についてはどこを見ればいいんでしょうか。」
などご意見頂いておりますので、
今回は、研究所や工場などで使用されるような有害な化学物質への対策と法的義務等について、例を挙げてご説明致します。
人体に有害な影響を及ぼすことが確認されている化学物質は「特定化学物質」とされ、曝露リスクを最小限に抑えるため、適切な管理と取り扱いに関する法的な基準が定められています。
この特定化学物質は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則などにより
規定されておりますが、かなり複雑に入り組んでおり、お役人の方々でさえも、解釈に難渋する傾向にあります。
特定化学物質は、危険性や有害性に基づいて、より注意すべき順に、第1類、第2類、第3類特定化学物質と分類され、
労働安全衛生法施行令の別表第三に列挙されています。
第1類特定化学物質は、「がん等慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、特に有害性が高いもの」であり、7種が該当します。
1. ジクロルベンジジン及びその塩
2. アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3. 塩素化ビフェニル(PCB)
4. オルト-トリジン及びその塩
5. ジアニシジン及びその塩
6. ベリリウム及びその化合物(合金は重量の3%を超える場合)
7. ベンゾドリクロリド
1-6の物質は、全体重量の1%を超える場合、7の物質は全体重量の0.5%を超える場合となっております。
第1類特定化学物質のうち、例えば、塩素化ビフェニル(PCB)は、電気絶縁性が高く、耐熱性のある粘性の液体で、コンデンサなどの
各種電気機器に使用されておりましたが、1968年にカネミ油症事件により毒性が社会問題となり、1972年以降、製造、
輸入及び新たな使用が原則禁止となっております。
 chip. The IC is placed on a reflective black surface, showing intricate patterns and conn.webp)
これら第1類特定化学物質は、完全に製造禁止というわけではなく、製造の許可を受けるべき有害物(製造許可物質)であり、
製造にあたり厚生労働省の許可を受ける必要があります。
第2類特定化学物質は、「がん等慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、第1類物質に該当しないもの」であり、60種が該当します。
1. アクリルアミド
2. アクリロニトリル
3. アルキル水銀化合物
・
・
35. 硫化水素
36. 硫酸ジメチル
(枝番あり)
第2類特定化学物質のうち近年有名となった物質には、1,2-ジクロロプロパンがあります。
この物質は臭気のある無色の液体で、金属用または印刷用洗浄剤として使用されておりますが、
長期間にわたる高濃度曝露により胆管がん発症につながる蓋然性が高いとされております。
1,2-ジクロロプロパンは、以前は規制対象ではありませんでしたが、印刷会社で胆管がんが複数名有意に高く発症したことから、
平成25年から特定化学物質へ追加されました。
このように、規制されていないものの、実は発癌性を有し、有害であったということがあり、規制されていないからといって、
何も対策をしなくて良いということは極めて危険なことであると言えます。
2021年4月1日には、溶接ヒューム、及び塩基性酸化マンガンが第2類特定化学物質として追加されたことも記憶に新しいかと思います。

第3類特定化学物質は、「大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質」で、8種が該当します。
1. アンモニア
2. 一酸化炭素
3. 塩化水素
4. 硝酸
5. 二酸化硫黄
6. フェノール
7. ホスゲン
8. 硫酸
第1類特定化学物質、第2類特定化学物質、第3類特定化学物質を合計すると75種類あり、各物質によって規制内容が異なりますので、
労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則を紐解いていくのは非常に時間がかかります。
厚生労働省からは、かなり前の資料になりますが、
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0306-9g.html
のような表が出されています。
「労働衛生のしおり」にも同様の表が更新され記載されていますので、各物質について参照しやすいようになっています。
特定化学物質障害予防規則では、これら特定化学物質の管理及び取り扱いについて規定しています。
特定化学物質を扱う際に、主にすべきこととして、
・特殊健康診断
・発散源の対策
・作業環境測定
・作業主任者の選任
があります。
ここでは第2類特定化学物質からひとつ、ホルムアルデヒドを例に取り、対策を考えていきます。
ホルムアルデヒドの場合は、1%以上の濃度を使用する際に適用されます。
特殊健康診断については、使用頻度や使用量をもとに、管轄の労基署等により判断が異なることもありますが、
使用量によらず使用頻度が週1回以上であることが健康診断実施の基準となることが多いようです。
とはいえ短期間しか使用しない場合はどうなのかといったご質問もたまにありますが、こちらは3ヶ月以上使用が一つの基準となっているようです。
また、屋外で使用しているだけだから問題ないのでは?というご質問も時折ありますが、こちらは屋外であっても屋内同様実施することとなります。
なお、派遣の場合は、一般的な健康診断は派遣元が実施しますが、特殊健康診断は派遣先が実施することとなっております。
ホルムアルデヒドや第3類物質の場合は、例外的に特殊健康診断の実施は必要ありません。
ホルムアルデヒドは、特殊健康診断の代わりに、労働安全衛生規則第45条に基づく、一般定期健康診断を、6ヶ月に1度以上の頻度で実施する必要があります。
発散源の対策は、密閉式、局所排気装置、プッシュプル型換気装置いずれにおいても対策が可能となっております。
作業環境測定は、基本的に第1類、第2類物質であれば、6ヶ月に1度以上の頻度で実施する必要があります。
ホルムアルデヒドの場合は、特別管理物質に該当しますので、30年間結果を保管する必要があります(通常は3年保管)。
なお、屋外の場合は、実施が困難であるため、作業環境測定は行わないことが一般的ですが、個人サンプリングにより、
測定することが望ましいとされています。
作業主任者の選任は、特定化学物質に該当すれば、どの物質であれ、どのような場面であっても、選任することとなっております。
上記、対策を怠る場合、行政指導の対象となり、改善が見られない場合は50万円の罰金等課せられることなりますので、要注意です。
また、忘れやすい事項として、塩酸は特定化学物質に該当しないのですが、扱う場合特定業務従事者に該当しますので、
6ヶ月に1度以上の頻度で特定業務従事者健康診断、及び歯科検診を実施する必要があるということです。
また、第3類物質である硝酸についても、特殊健康診断を実施する必要がないですが、同様に6ヶ月に1度以上の頻度で
特定業務従事者健康診断及び歯科検診を実施する必要がありますのご注意ください。
特定化学物質は、その取り扱いにおいて高いリスクを伴いますが、適切な管理と対策を講じることで、現場での安全対策を徹底され、
労働者の健康を守り、企業のリスクを取り除くことに繋がりますので、ご参考になりましたら幸いです。
この記事の関連記事

有害かも知れない化学物質を扱ってますがどうしたらいいでしょうか?
「ぱっと見て法的な規制に該当しなさそうだったので何もしていま…
「ぱっと見て法的な規制に該当しなさそうだったので何もしていま…

熱中症対策で御社の生産性が上がります
熱中症とは、高温多湿等の暑熱環境において体温調節が困難となり…
熱中症とは、高温多湿等の暑熱環境において体温調節が困難となり…

専属産業医が他事業場で嘱託産業医としても選任されるのは問題ないですか?
「専属産業医として勤務しておりますが、週3の訪問なので、他の…
「専属産業医として勤務しておりますが、週3の訪問なので、他の…

有機溶剤はたまに使うだけなので特殊健康診断しなくて大丈夫ですよね?
「有機溶剤??うちは有機溶剤は扱ってないです。スプレーですか…
「有機溶剤??うちは有機溶剤は扱ってないです。スプレーですか…
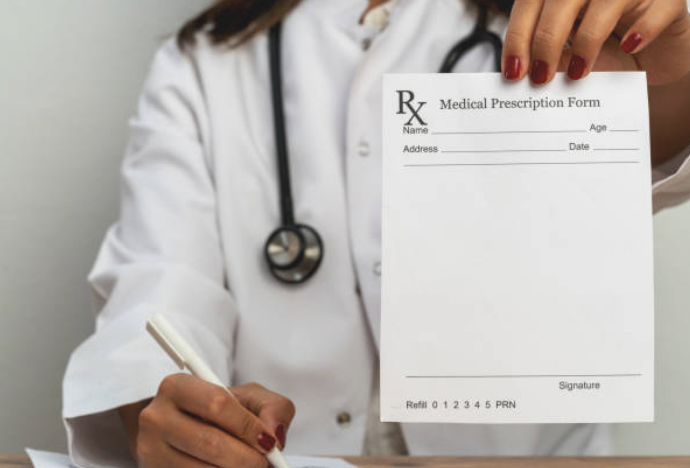
従業員の健康に関する個人情報は外部に漏れている場合がありますが大丈夫ですか?
個人情報には十分な配慮が必要な世の中になっておりますが、従業…
個人情報には十分な配慮が必要な世の中になっておりますが、従業…

当サイトを利用するメリットと、よく頂く心配点
皆様 産業医explorerへのご訪問ありがとうござ…
皆様 産業医explorerへのご訪問ありがとうござ…











